日本最大級の学生ビジネスコンテスト「キャンパスベンチャーグランプリ(CVG)東京大会」で、明星大学経営学部・伊藤智久教授のゼミから2チームがファイナリストに選出されました。同一ゼミから複数チームが進出するのは極めて珍しく、異例の快挙です。2025年12月9日、霞ヶ関の霞山会館で開催されるファイナル審査会に向け、両チームは最終準備を進めており、その挑戦に期待が高まっています。
学生ビジネスコンテスト最大級の挑戦
CVGは1999年に大阪で始まり、国内外でも最も歴史ある学生向けビジネスコンテストの一つで、学生起業家の登竜門として知られています。現在、全国8地域(北海道、東北、東京、中部、大阪、中国、四国、九州)で、多くの企業や公的組織の協力のもと地域大会を開催しており、第22回目を迎える東京大会は、その中でも特に大きなエリア(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県)の大学の学生たちが参加をし、大賞を目指します
昨年度も伊藤ゼミから東京大会のファイナリストが誕生し、MIT賞(マサチューセッツ工科大学賞)を受賞しました。今年度はその勢いをさらに加速させ、2チームがファイナリストに選出され、ファイナル審査会に挑戦します。「先輩に続こう」という思いがゼミ全体に広がり、熱気に包まれています。
挑戦の集大成へ、「全力を出し切る」決意
今回伊藤ゼミから2チームがファイナルに選出されたことで、代表者2人は「ファイナル当日、仲間が同じ会場にいることで緊張しすぎず臨めると思う」「一緒に仲間がいると安心感がある」と話します。互いに刺激を受けながら取り組みを続けてきた2人のファイナル審査への意気込みを紹介します。また、指導する伊藤智久教授からもメッセージをいただきました。
事業名:eスポーツによる学校間の地域クラブ「CLUB AILE」
1人目のファイナリストチームの代表者である酒井陽飛さん(経営学部経営学科3年)に意気込みを伺いました。
ー応募した事業内容の概要は?
最初は「部活動が教員にとって負担である」という社会課題に注目しました。ニュースや現場の声を調べる中で、教員の負担軽減だけでは競合との差別化が難しいと感じ、何度もピボットを重ねました。その過程で、不登校児童が増えている現状に目を向け、居場所づくりの重要性に気づきました。そこで、eスポーツを活用し、不登校の生徒や部活動にeスポーツがない中学生に新しいコミュニティを提供する事業を考えました。コミュニケーション不足や社会経験の不足を補える場をつくることが狙いです。
ー特にアピールしたい点は?
「不登校支援×eスポーツ」という切り口です。伸びているeスポーツ市場を活用しながら、不登校の子どもたちに居場所を提供する仕組みを考えました。また、自治体と協力して実証に向けて動いている点も特徴です。単なるアイデアではなく、現場と連携して進めていることが強みだと思います。
ー苦労した点は?
最も大変だったのは、ゼミ合宿の中間発表直前に事業案を白紙に戻したことです。差別化ができていないと感じ、合宿中はほぼ寝ずにチームで資料を作り直しました。ゼロから再構築する中で、メンバー全員がアイデアを出し合い、必死に考え抜いた経験は大きな財産になっています。
ーファイナル審査会に向けた意気込みは?
ここまできたら結果にとらわれず、不登校の子どもたちにこの事業を本当に届けたいと思っています。今は自治体と協力しながら実証に向けて動き始めていて、ただのアイデアで終わらせたくありません。伊藤ゼミの先輩の清水さん(※関連リンク参照)が昨年度のこの大会で受賞した道を開いてくれたことは、大きな刺激になっています。その先輩を超えて、全国大会に出場し、トップを取ることが目標です。もちろんプレッシャーはありますが、ここまでチームで積み重ねてきた努力を信じて、最後までやり切ります。
事業名:匿名と共感のつながり「empath」
2人目のファイナリストチームの代表者である矢島寛大さん(経営学部3年・伊藤ゼミ)に意気込みを伺いました。
ー応募した事業内容の概要は?
最初は「中小企業のDX化が遅れている」という課題に注目していました。しかし、商工会議所の方に話を聞いた際、「人手不足の原因は学生に中小企業の魅力が伝わっていないこと」という現場の悩みを知り、方向性を大きく変えました。そこで、学生と中小企業がフラットにつながれる仕組みを考え、匿名性と共感を軸にしたマッチングサービス『empath(エンパス)』を提案しました。企業名や給与に左右されず、理念や価値観に共感できる相手を選べる仕組みです。
ー特にアピールしたい点は?
このサービスの特徴は「匿名性」と「共感」という視点です。従来の就職活動は企業名や待遇で判断されがちですが、私たちはそれを排除し、価値観や理念でつながる仕組みを作りました。これにより、学生は自分に合った企業を見つけやすく、企業側も本当に自社の考え方に共感してくれる人材と出会えます。さらに、現場の声をもとに設計しているため、実際の課題解決に直結する点も強みです。
ー苦労した点は?
人材のマッチングサービスは新規性が薄いと言われる中、何度もゼロに戻って議論しました。現場の声を諦めずに突き詰めて生まれたアイデアです。チームで何度もアイデアを出し合い、試行錯誤を繰り返した過程は本当に大変でしたが、その分、納得できる形に仕上がったと思います。
ーファイナル審査会に向けた意気込みは?
そもそも、ファイナル審査会に進出できると思っていなかったので驚きましたが、期待に応えられるよう全力を尽くします。結果よりも、自分の実力を出し切ることに集中したいです。ここまでチームで何度も壁を乗り越えてきたので、その努力を信じます。
伊藤智久教授
どちらのチームも、ゼミナールの活動を通して、自分たちの興味や課題意識の探索からスタートし、ここまで試行錯誤を重ねながらビジネスモデルを構築してきました。その姿勢や活動そのもの自体が、まさに“起業ビジネスを学ぶ”ということだと思います。
ファイナル審査会では、緊張せずに普段通りのプレゼンをしてほしいです。コンテストの結果はどうであれ、挑戦するプロセスの中で得た学びや成長を自信に変えて、さらなる挑戦を続けてくれることを期待しています。
両チームの挑戦にどうぞご注目ください。

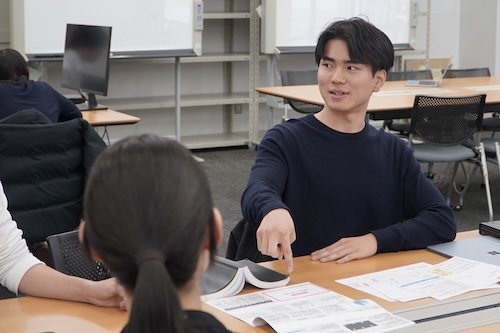 酒井陽飛さん
酒井陽飛さん
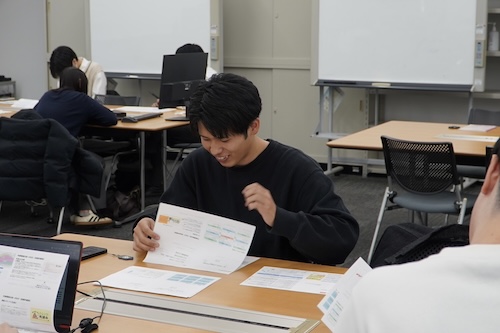 矢島寛大さん
矢島寛大さん
 伊藤智久教授
伊藤智久教授
 ゼミ全体でもこの快挙に盛り上がっているそうです(ゼミの様子)
ゼミ全体でもこの快挙に盛り上がっているそうです(ゼミの様子)

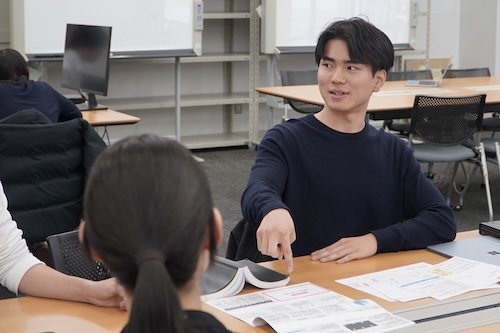 酒井陽飛さん
酒井陽飛さん
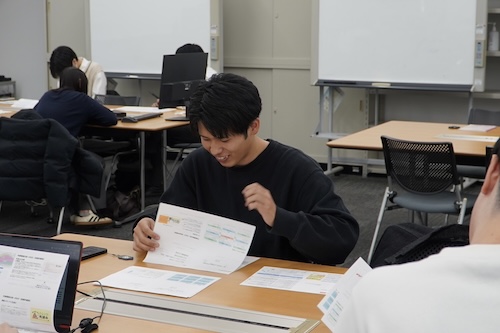 矢島寛大さん
矢島寛大さん
 伊藤智久教授
伊藤智久教授
 ゼミ全体でもこの快挙に盛り上がっているそうです(ゼミの様子)
ゼミ全体でもこの快挙に盛り上がっているそうです(ゼミの様子)