明星大学データサイエンス学修プログラム(リテラシーレベル)
本プログラムで身につけることのできる能力
授業の方法・内容
実施体制
スクロールできます
| 委員会等 | 役割 |
|---|---|
| データサイエンス学環長 | プログラム(科目)実施責任者 |
| データサイエンス学環 ※1 | プログラムの改善・進化、自己点検・評価 |
| データサイエンスリテラシー運営チーム ※2 | 授業計画の策定、教材開発・学習システム開発、授業運営・実施 |
- ※1データサイエンス学環にデータサイエンス教育検討委員会を置き、データサイエンス教育の充実・改善・進化、および学内外への展開を見据えた教育プログラムの開発・整備を行うこと、ならびに自己点検・評価についての検討を行っています。
- ※2データサイエンスリテラシー運営チームは、科目担当教員をはじめ、教材や学習システムの開発・整備・改善を行う教員および学生(TA・SA)により構成されています。また、TA・SAの養成も行っています。
自己点検結果
明星大学データサイエンス学修プログラム(応用基礎レベル)
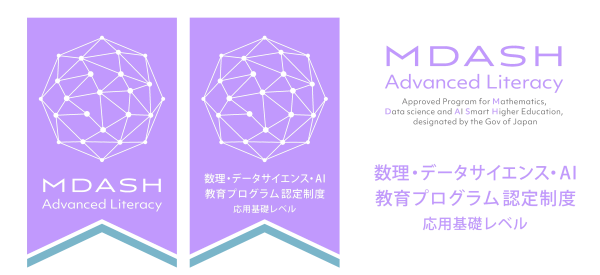
授業内容
スクロールできます
| 科目名称 | 単位数 | 配当年次 | 授業内容 | モデルカリキュラム対応箇所 |
|---|---|---|---|---|
| データサイエンス演習1 | 2単位 | 2年 | 数理・データサイエンス・AIに関してこれまでに身に付けた知識・技能を基に、主にPythonを用い、演習を通じて、各種データの収集・加工・分析の基礎を身に付ける。 具体的な事例を通じた演習を行うことで、データの収集・加工・分析の一連の過程を理解するとともに、数学や統計学をベースとしたデータサイエンスの理論とその実践との関連に自ら気付きを得ることで、より深い知識の理解と技能の体得を目指す。 |
1-2: 分析設計、 2-2: データ表現、 1-3: データ観察、 1-4: データ分析、 1-5: データ可視化、 2-5: データ加工 |
| AI・機械学習1 | 2単位 | 2年 | 機械学習の基本的な手法を取り扱う。人工知能、機械学習とは何かを説明し、機械学習の基本手法と深層学習の基礎を解説する。また、深層学習や強化学習、生成AIの基本的な考え方にも触れる。いろいろな機械学習アルゴリズムの目的や適用範囲を実例とともに紹介する。 | 3-1: AIの歴史と応用分野、 3-2: AIと社会、 3-3: 機械学習の基礎と展望、 3-4: 深層学習の基礎と展望、 3-5: 生成AIの基礎と展望、 3-10: AIの構築・運用 |
| 統計学1 | 2単位 | 1年 | 種々の分野におけるデータから有用な情報を得るためには、統計学の知識を身につけることが必須である。本講義では統計的なものの見方や考え方を身につけ、種々の統計学の共通の基礎である推測統計の推定論について理論面を中心に学ぶ。 統計学の基礎知識である統計的推定論の理論と応用を身につけ、データサイエンス分野で活躍できるようにする。 |
1-6: 数学基礎 |
| 線型代数学1 | 2単位 | 1年 | 線型代数学は、情報・理工系の多くの分野において登場する数学の基礎となる体系である。幾何学的なベクトルやベクトルの写像等を拡張した線型空間の概念を理解することを目標とする。まずは具体的なベクトル・行列計算等を行うことができるように、更には連立一次方程式を解く等の応用にも使うことができるようになることを目指す。はじめは実数上の2、3次元におけるベクトルや行列の幾何学的意味を考えながら、その計算に慣れ親しむ。その後、n次元や複素数に拡張し、掃出し法等の応用も修得し、抽象線型空間の理解に至る。 | 1-6: 数学基礎 |
| 基礎解析学1 | 2単位 | 1年 | データサイエンスをはじめ、自然科学や社会科学を専攻する上で必要となる解析学の基礎を身に付けるため、本科目では1変数実関数に対する微分法、積分法を学ぶ。まず、集合、関数、数列、収束、極限などの微分積分学に必要な概念を理解し、1変数実関数の微分積分を理解するとともに、具体的な関数の微分、積分の計算ができるようになることを目指す。そして、基礎解析学がデータ分析やAI・機械学習でどのように役立っているかを理解する。 | 1-6: 数学基礎 |
| プログラミング概論 | 2単位 | 1年 | プログラミングの初歩的な概念および文法について学ぶ。プログラミング言語とプログラミング技術の基礎を理解する。フローチャートを用いた論理的記述に始まり、プログラムの構造、プログラムの書き方、デバッグについて学ぶ。なお、プログラミング言語はPythonとCを扱う。 | 1-7: アルゴリズム、 2-2: データ表現 |
| プログラミング演習 | 2単位 | 1年 | 計算機としてのコンピュータの概要を学ぶことを通して、Pythonによるプログラミングの基礎を身につける。さらに、Pythonで学んだことをもとに、C言語でも同様の簡単なプログラムを作成できるようになることを目指す。 | 2-7: プログラミング基礎 |
| データサイエンス概論1 | 2単位 | 1年 | データサイエンスとは、科学的手法を用いてデータから価値のある情報や知見を生み出す学問領域である。データサイエンスが世の中でどのように用いられ役立っているかを概観し、他の学問領域とどのような関係にあるのかを理解し、今後のデータサイエンス学修・研究のロードマップを設計できるようになることを目標とする。 現代のデータサイエンスで用いられる主な科学的手法は、統計学と人工知能である。具体的な応用例を交えつつ、これらの手法が、自然現象や社会現象の予測や識別においてどのように使われるのかを紹介する。 |
1-1: データ駆動型社会と データサイエンス、 2-1: ビッグデータと データエンジニアリング |
| データサイエンス概論2 | 2単位 | 1年 | データサイエンスを活用した研究や、連係学部の関連科目を、専門分野ごとにオムニバス形式で紹介する。情報学部、理工学部、経済学部の教員がそれぞれ4回ずつ担当する。また3回の授業回を使い、紹介された各分野の研究・活用事例について、自らの興味関心や社会的必要性に照らし合わせながらまとめ上げ、さらにそれらを相互に批評する。 | 1-1: データ駆動型社会と データサイエンス |
実施体制
スクロールできます
| 委員会等 | 役割 |
|---|---|
| データサイエンス学環長 | プログラム(科目)実施責任者 |
| データサイエンス学環 ※1 | プログラムの改善・進化、自己点検・評価 |
| データサイエンス学環 ※1 | 授業計画の策定、教材開発・学習システム開発、授業運営・実施 |
- ※1データサイエンス学環にデータサイエンス教育検討委員会を置き、データサイエンス教育の充実・改善・進化、ならびに自己点検・評価についての検討を行っています。

