明星大学通信制大学院 研究領域と指導教員の
通信制大学院とは
自宅学習を中心に、
大学でも、現場でも、学ぶ。
大学


ゼミナール
不定期開講の対面型授業 学生同士の議論やOB・OGの参加も
担当教員の指導のもとで、多様な視点を持つ学生たちが意見交換し、ときにはOB・OGも参加。教員により、遠隔会議システムによる指導を行うこともあります。
スクーリング
年3回開講の対面型授業 教員から直接指導を受けられる
担当教員による直接指導のため、研究の深掘りや質問ができます。研究仲間との議論により、新たな視点を獲得できるのも魅力です。
自宅
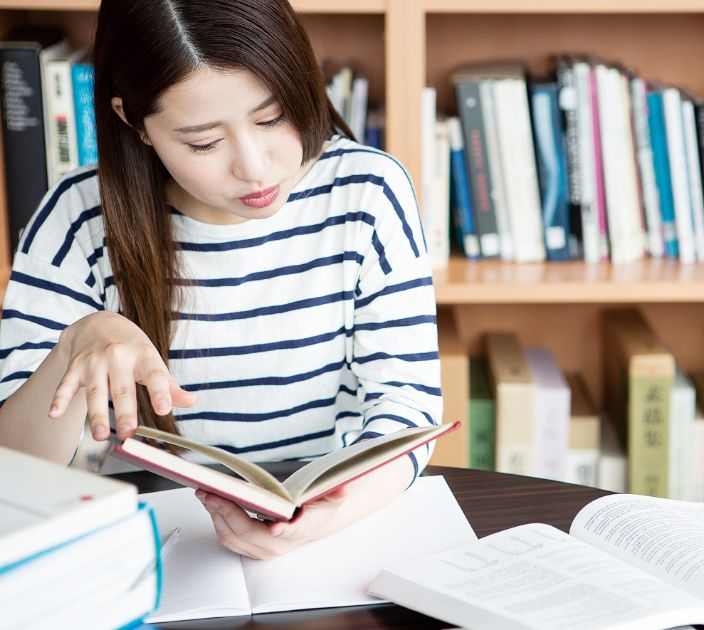
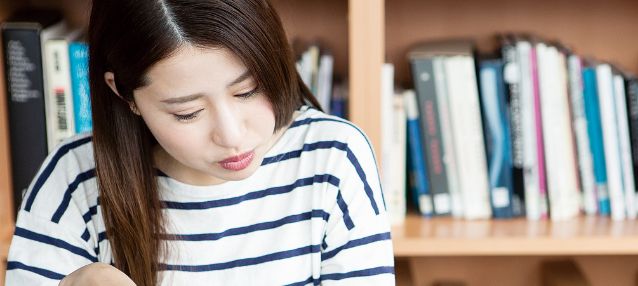
自宅学習
レポート学習で学びを深める
自学自習の成果を文書化し、丁寧な添削を受けることで、効果的に学びを深められます。
大学の図書館を有効に活用
大学の図書館(28号館)と資料図書館で、合わせて約90万冊を所蔵。文献複写も随時対応しています。
現場


フィールドワーク
研究テーマの現場を訪れ
その実態を調査する
教育学は、実践的な要請から発する学問分野です。現場の調査を実施し、新たな課題や解決策の発見につなげましょう。
職場での発見
現場の課題が研究の材料となり
研究の成果が現場に活かされる
教員として働きながら学ぶ学生は、日々の現場での発見を研究に取り込むとともに、日々の研究の成果を現場で実践・検証していきましょう。
大学院の主な役割として、研究者養成と高度な専門知識・技術をもつ人材の養成などがあげられます。
近年の社会や技術は高度化・複雑化・情報化・国際化などをうけて、めざましく発展しています。
このような状況の中で、大学院はより高度な専門的能力を養成する場としての重要性を高めています。
しかし、職業をもつ社会人の場合、通学による就学は困難なケースが少なくありません。
通信制のメリットは仕事をもっている方や、様々な事情で通学での就学が叶わない方にも学習・研究の機会を
提供できることだと思います。実際に学習・研究を進める際は個々の自主的・自立的学習が主となります。
こういった通信教育の性格上「このような理解の仕方でよいのだろうか」というような疑問が生じた時、
直ちに解決することが難しい点がデメリットとしてあげられます。
また独りで学習を進めていくことに不安を感じることもあるでしょう。
通信教育のデメリットを減じるために、明星大学通信制大学院ではEメール・郵便等による質問の受付、
スクーリング(面接授業)の機会を拡充、院生の学習・研究を担当教員及び大学院スタッフがサポートしています。
3つの研究領域
本学通信制大学院は、博士前期課程・博士後期課程ともに、主に「子どもの教育と成長」に携わる社会人を対象として、専門知識や技術の修得、研究能力の向上を支援しています。研究領域は、近年とくに発展が望まれている以下の3つです。
授業研究領域学校教育などで展開される授業等についての研究
教育現場で実践されている授業の課題を考察し、より質の高い授業の実現を目指します。教育学の基礎を学んでいない教育従事者が多い実情を踏まえ、まずは基礎固めを重視。一方で、一般的な教育論を視点を変えて見直し、先入観にとらわれない姿勢を身につけます。自らの専門性により狭まった視野を、研究を通して広げていくことが肝心です。実践と理論を繰り返し行き来して、知識や経験を「使えるかたち」に変えていきます。
[ 修士論文研究テーマ一例 ]
- ■指導要録における行動の記録の変遷と評価項目等に関する研究
- ■教員の育成指標におけるカリキュラム・マネジメントの要素に関する研究
- ■カリキュラムマネジメント・モデルを踏まえた学校における食育推進のためのチェックリストの開発
幼児教育研究領域家庭、子どもを取り巻く社会環境、保育方法などについての研究
子どもの発達、教育方法を中心に、子育て支援のかたちを幅広く研究。家庭環境や保育施設など、幼児教育を取り巻く問題はますます多様化しています。こうした問題の解決に向けて、幼児教育の現場にいる方々がそれぞれの課題を共有し、ともに研究することで、解決を目指していきます。今の仕事のステップアップはもとより、生涯をかけて解決すべきテーマにじっくりと取り組むことができます。
[ 修士論文研究テーマ一例 ]
- ■地域子育て支援拠点事業による保護者支援のあり方 ー相談内容の分析による子育て支援への提案ー
- ■子どもの歌の歌詞にみるともだち観 ー幼稚園教育要領の領域「人間関係」成立以後に着目してー
- ■小山内薫の教育観に関する研究 ージャック=ダルクローズの教育観から受けた影響を中心にー
障害児者教育研究領域障がい児者の発達、支援についての研究
多様な障がい特性の理解を土台とし、障がいのある子どもの教育・支援・発達・評価などについて包括的に研究。理想の障がい児者教育の実現を目指して、障がい児者に対する支援計画の構築と実施、障がい児者を抱える家族の支援、音楽療法の方法論の研究などに取り組んでいます。障がい児者教育においては、一人ひとりの違いへの深い理解が重要です。それが個性を伸ばす、理想の教育の第一歩となるからです。
[ 修士論文研究テーマ一例 ]
- ■作業療法士による特別支援教室への介入効果において ー感覚統合理論に基づいた自立活動における運動・動作の活動を通してー
- ■児童を対象とした視覚障害理解を催促する授業における効果的な言語表現
- ■校内におけるインクルーシブ教育充実のための教員支援 ー特別支援教室専門員の役割に着目してー
指導教員の研究紹介
授業研究領域
前期
後期
教育心理学、認知心理学
[ 研究テーマ ]
教育場面におけるコミュニケーションの特徴と学習過程・学習効果の関係性の解明、読み書き能力と認知機能の関係性の解明
学術博士(Ph.D.)。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。イリノイ大学(University of Illinois at Urbana -Champaign)大学院教育学研究科博士課程修了。国立国語研究所研究員、政策研究大学院大学客員教授などを経て本学へ。心理学や会話分析などのアプローチで、「読み書きの認知過程」や「コミュニケーションと学習効果の関係性」を解明する研究を進めている。
- MESSAGE
- 現在は、主に、教授場面における教授者と学習者および学習者同士の相互作用と学習効果に関する研究、ディスレクシア児の読み書き行動と認知特性に関する研究に取り組んでいます。建設的に研究を進めていくためには、問題発見力、研究テーマ・方法に関する知識・技能、洞察力、分析的思考力、論理的思考力、創造力などに加え、一つのことを粘り強く探究していく能力や幅広い社会的視野が非常に重要です。本学の学生には、実験・観察・調査などの様々な研究方法を用いて、各々の研究テーマを心理学的観点から実証的に研究していくプロセスを指導しています。教育活動・現象に関する法則を是非一緒に解明していきましょう。
前期
後期
日本教育史、教育思想
[ 研究テーマ ]
森有礼の体育論、児玉九十の教育思想など
明星大学大学院人文学研究科教育学専攻(博士前期課程、博士後期課程)修了。博士(教育学)。明星大学で学び、他大学の助教として勤務しながら、初代文部大臣・森有礼の体育論に関する研究で博士の学位を取得。現在は、本学の初代学長・児玉九十の教育思想についても研究を行う。
- MESSAGE
- 初代文部大臣・森有礼の体育論をテーマに、森が日本の教育に導入した合理主義的な身体観を起点とし、西洋の教育思想などを踏まえ新たな検討を加えた研究を行っています。また、私学の教育者として多く実績をもつ明星大学初代学長・児玉九十の教育思想についても研究しています。今日の教育的事象を検討するとき、過去の教育に対して歴史的な背景を踏まえた上で意義や成り立ちを理解することが必要になります。教育に関する問題解決のために、物事の事実関係、価値や役割などをあらためて検討するのが教育史の役割です。ご自身の教育的課題を見つめ、深化させる視点をもった方にぜひ学んでいただきたいと思います。
前期
後期
教育工学、教師教育
[ 研究テーマ ]
教師の授業力量向上のための研修、
ICTを活用した授業設計、情報活用能力の育成、
国際教育協力における授業研究
関西大学大学院総合情報学研究科・博士課程後期課程修了。博士(情報学)。国内外の教育機関、NPO、NGOと連携しながら、教師の授業力量向上を目指した教員研修や授業研究など、学校現場との協働を重視した研究を続けている。さらにICTを活用した授業設計や情報活用能力の育成、国際教育協力の現場において授業研究の仕組みづくりなど、現職教員の専門性を高める支援にも携わる。
- MESSAGE
- 教育現場や社会で活躍する方々の実践には固有の価値と知見があります。大学院での学びは、そうした実践を理論的に捉え直し再構築することで、より高い教育的意義へと昇華させる機会となります。私の専門である教育工学は、ICTやメディアを活用した学習環境の設計、研修や教材の開発、教育実践の評価と改善などを扱う学際的な学問です。本研究科での学びは、教育現場の改善にとどまらず、自らの実践を学術的に整理し、理論的な裏づけをもって広く社会に提案することを目指します。量的・質的な分析手法を通して、実践の意味や効果を言語化し、他者と共有可能な知見として構築していく、その過程を通じて、実践者としての視野を大きく広げることができます。現職教員をはじめ、企業・地域・国際協力など教育に関わる方々と、現場に根ざした研究を進めることを楽しみにしています。
前期
後期
教育社会学、教育調査
[ 研究テーマ ]
小中高生の学習と生徒文化に関する実証的研究
東京理科大学理工学部卒業。東京大学大学院教育学研究科比較教育社会学コース修士課程および博士課程修了。博士(教育学)。東京大学大学院教育学研究科研究員などを経て現職。教育社会学を専門とし、さまざまな大規模質問紙調査データの分析を行っている。
- MESSAGE
- 教育社会学の研究対象は、学力格差・友人関係・学歴社会・親子関係・ジェンダーなど多岐にわたりますが、常識に捉われず、データに基づいて教育現象を考察することが特徴です。大学院生は、各自が定めた研究テーマについて、文献講読や調査の実施・分析を行います。学校や社会で当たり前と思われていることを改めて問い直したい方、教育問題や社会問題を実証的に分析したい方に向いています。目の前にいる子供がいかに楽しめるかだけではなく、現代教育の課題や今後の在り方を、広い視野で考えられるようになっていただきたいです。
前期
後期
教育行政学、教育政策研究
[ 研究テーマ ]
教育行政・学校・教職員の社会科学的研究、
教職員のウェルビーイングに関する実証的研究
東北大学教育学部卒業、東北大学大学院教育学研究科博士前期課程及び博士後期課程修了。博士(教育学)。日本学術振興会特別研究員、独立行政法人教職員支援機構研修特別研究員等を経て、2023年4月より現職。専門分野は教育行政学。現在は産業衛生学や産業・組織心理学等の隣接学問領域の分析枠組み・分析方法を用いて、教職員の労働時間・ワークライフバランス・ウェルビーイング・健康に関する実証研究(主に計量分析)を進めている。
- MESSAGE
- 教育は誰もが経験するため、各自の経験や印象に基づいた教育政策に関する議論があり、こうした議論の中には客観的な根拠が不十分なものや事実誤認に基づくものもあります。そのため、大学院生として教育行政・教育政策研究に励む皆さんには、社会科学としての教育行政学を意識し、教育事象をめぐる当たり前を疑う姿勢を身につけ、教育事象を読み解くために必要となる理論や分析方法を修得することを期待します。教育行政学は教育行政を対象とした学問とも言われ、教育行政を読み解くための手がかりは政治学、行政学、社会学、経済学、心理学といった隣接学問領域にあります。そのため、隣接学問との対話を重視した指導を行います。ともに教育行政・教育政策研究を盛り立てていきましょう。
前期
後期
教育方法学、教育評価
[ 研究テーマ ]
生活知と学校知の融合を目指した生活作文教育の研究、
児童生徒に寄り添い、その成長の姿を捉える教育評価の研究、
学校教育で育む資質・能力を伸ばす教育方法論の構築と検証
京都大学大学院教育学研究科学校教育専攻(博士前期・後期課程)修了。博士(教育学)。東京学芸大学助教、琉球大学教育学部講師・准教授を経て本学へ。日本独自の授業論・評価論などについて大学院の仲間とともに探究しながら、上海などの教育先進地のカリキュラム開発論や多種多様な探究の方法論について研究している。
- MESSAGE
- 教育方法学は、さまざまな現場で教育実践に携わる方、これから学校教育の現場で働こうとしている方にとって、最も必要とされる学問の1つです。なぜなら、目の前にいる児童生徒たちのさらなる成長の可能性を見出すために、自らの人づくりの技と感性を磨き、理論と実践を洗練させ、創造していかなければなりません。私もその必要性に迫られた一人に過ぎませんでした。この学問の懐の深さに魅了され、今も研究者の道を歩み続けています。主な研究方法は文献研究とフィールドワークです。必要に応じて、アンケート調査の手法も取り入れています。本日の学校教育のあり方や授業論・評価論などについて抱えている問題意識を明確にし、それを研究テーマとして転化し、納得のいく研究を結ぶまでのプロセスを一緒に考え、進めてみませんか。
幼児教育研究領域
前期
後期
音楽教育学、リトミックを活用した
教育・保育
[ 研究テーマ ]
身体運動を活用した音楽教育法リトミック
博士(教育学)。国立音楽大学音楽学部教育音楽学科Ⅱ類(リトミック専修)卒業後、ニューヨーク、ダルクローズ音楽学校にてリトミック国際指導者免許を取得。その後、明星大学通信制大学院修士課程、大学院博士後期課程を修了。音楽と身体運動の組み合わせで、子どもたちの人間性を総合的に高めることを研究テーマとする。
- MESSAGE
- 音楽教育の目的とはどのようなものでしょうか? 音楽教育を通じて、どのような子どもたちを育成したいのでしょうか? 先ずは目的を明確にし、そこへ至るための方法や技術を検討する必要があります。プラトンは『国家論』の中で、音楽教育をすることで品性のある子どもを育てることができると言っています。リトミックを創ったジャック=ダルクローズは、リズムに合わせた身体運動を行う音楽教育によって子どもたちの集中力、思考力、社会性を高めることができると考えていました。先人たちの考え方を知ることにより、私たちの実践もより深いものとなるでしょう。
前期
後期
児童発達学、保育学
[ 研究テーマ ]
心理的拠点形成と保育環境、3歳未満児の発達と保育、乳幼児の生活とあそび、保幼小連携
乳幼児の発達と保育を専門とする。現場での保育と発達相談の経験を活かし、保育方法、保育内容、発達心理学、乳幼児保育学など、幅広いテーマで研究を手がける。博士(教育学)。
- MESSAGE
- 乳幼児保育学は単なる技術論ではありません。深い人間洞察に基づいて子どもや保育を考える哲学でもあり、人としての心の有り様や人間関係を捉え考察する心理学でもあり、子どもたちが平等に幸せに暮らしていくためのあり方を考える福祉学でもあり、それらを踏まえて環境や働きかけの方法・内容を考え、質の高い保育を追究する教育学でもあります。幼児教育研究領域を志願される方は、現場経験のある方が多いかと思いますが、子どもとの生活は発達的事実の宝庫です。沸々と生まれる疑問や研究的関心をそのままにせず、ぜひ、研究活動に繋げて頂きたいと思います。通信制大学院は、そのための方法論を学ぶところです。みなさんの新たな挑戦が実り多きものになるよう、一緒に学び合っていきましょう。
前期
後期
日本近代文学、児童文学
[ 研究テーマ ]
日本近代文学における子どもの存在
立教大学大学院文学研究科日本文学専攻博士後期課程修了。近代以降の文学において、子どもの存在がどのように描かれてきたのかという視点で文学作品を分析し、現代の子どもを取り巻く状況がどうあるべきかについて考える。
- MESSAGE
- 国語教育と児童文学との関わりに注目し、近代以降、現代に至るまでの子どもを取り巻く教育の場の変遷と国語教育のありようを明らかにすることを目標にしています。どの研究分野でも、近年強調されているグローバルな視点を持つことは大切であり、学問領域を越境した視野に立つことは研究の活性化に繋がると考えます。自分が専攻する分野だけではなく、幅広い知識を学び修得しようという意欲を持って積極的に研究に取り組む学生の入学を希望しています。研究の基礎を学び、自分独自の研究成果を出すという目標に向けて努力して頂きたいと思います。
前期
後期
社会学、社会福祉学
[ 研究テーマ ]
保育・教育・福祉などに対し社会政策の変容が及ぼす影響
上智大学大学院文学研究科社会学専攻博士後期課程単位取得満期退学。子どもの養育に関する社会システムとしての保育・教育・福祉などの教育実践やケア実践に対して、社会政策の変容が及ぼす影響について研究。社会福祉士などの資格を持ち、昭島市子ども子育て会議委員長なども務める。
- MESSAGE
- 現在の日本では、人口構造の変容や家族扶養規範の変容、子どもの位置づけの変容などによって、私的領域としての家族と公的領域としての国家・社会の関係の再考が必要とされています。そこで、子育ての実践の担い手である家族や専門職の役割葛藤やアイデンティティ・クライシスといった問題を、個人の内面における心理現象や、個別の組織の抱えるディレンマとしてではなく、徹底して社会構造や社会関係に埋め込まれた社会的現象として理解し、問題全体に新たな光を当ててその深層を「発見」していきます。様々な矛盾や問題を解きほぐしていくことで、社会的な多様性が認められる社会の構想に繋げていきたいと考えています。
障害児者教育研究領域
前期
後期
特別支援教育、障害児者心理学
[ 研究テーマ ]
知的障害児者のQOL(生活の質)とキャリア支援研究、発達障害児を対象としたソーシャルスキル研究、
障害理解教育に関する研究
日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター研究員、愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所研究員を経て、現在、明星大学教育学部教育学科特別支援教員コース教授。臨床心理士、特別支援教育士。東京都教育委員会の自閉症教育研究プロジェクト委員、青梅市教育委員会の特別支援教育協議会委員等も務める。
- MESSAGE
-
研究テーマの一つである「知的障害児者のQOL(生活の質)とキャリア支援研究」では、特別支援学校高等部や福祉施設を対象に、生きがいや幸福感等、豊かで充実した地域生活に資する支援方法について調査等を行っています。
通信制大学院を受験される方々の多くは、豊かな社会経験をお持ちかと思います。その中で培った見識等を研究論文という形で対象化することにより、今までの考え方が整理され、そこから更に新たな知見や課題が見えてくるのではないでしょうか。受動的ではなく、問題意識を持って、主体的且つ自立的に研究テーマに取り組んでください。
前期
後期
特別支援教育、療育、音楽療法
[ 研究テーマ ]
特別支援教育、母親支援、支援方法
東京学芸大学音楽科卒業、養護学校の音楽教師を経て、横浜国立大学大学院博士課程、東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻博士課程修了。保健学博士。様々な配慮を要する乳幼児から学童期を中心に家族を含めた早期発見・早期支援や支援方法についての研究を行う。近年は、母親支援を中心に支援員の育成や支援のシステムについても関心を寄せる。
- MESSAGE
- 特別支援教育の中で、主に微細運動のアセスメント、音楽療法、母親支援など、実践で使える方法論を研究していきます。これまでは配慮を必要とする子どもに対して周囲の人々がバラバラに支援をしていましたが、それらをいかに共有化・システム化していくのかが今の課題です。何のためにこの分野の研究をするのかといえば、子どもやご家族に貢献するためだと思います。その気持ちが揺らがずに真理を追究できる学生と出逢いたい。多くの特別な配慮を必要とする子どもたちは皆さんの学びを待っています。専門性のある支援者が少なく人材不足の領域です。ぜひ生涯学び続けることのできる素晴らしい人生の入り口に立っていただきたいと思います。
前期
特別支援教育、教材教具の開発、美術教育
[ 研究テーマ ]
強度行動障害のある児童生徒への教育的支援、
視覚的な支援を活用した自閉症スペクトラム症の児童生徒への教育(構造化による指導)、特別支援教育の場における美術教育
早稲田大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻修了。多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻修了。青年海外協力隊(現JICA海外協力隊)へ参加後、東京都特別支援学校教員として教育活動に従事しながら実践研究及び学校の教育力向上のための教育研究に携わる。長年、学齢期の強度行動障害に関する実践及び研究を続けている。
- MESSAGE
- 「特別支援教育元年」とも呼ばれる2007年から現在に至るまで、教育現場における特別なニーズは拡大の一途を辿っています。現行の教育制度をもってしても、全ての子どもに対する最適化された教育は途上の中にあるといえます。私たち教師は、個々の子どもの困難に対して適切な教育的配慮を実行できる実践者であることが求められており、それは理論との往還によって形づくられるものと思います。眼前にいる子どもの姿を確かな観点から理解し、子どもから学ぶという教師の「あり方」を土台に、自らの専門性を高めていく学びを実現していきましょう。
















