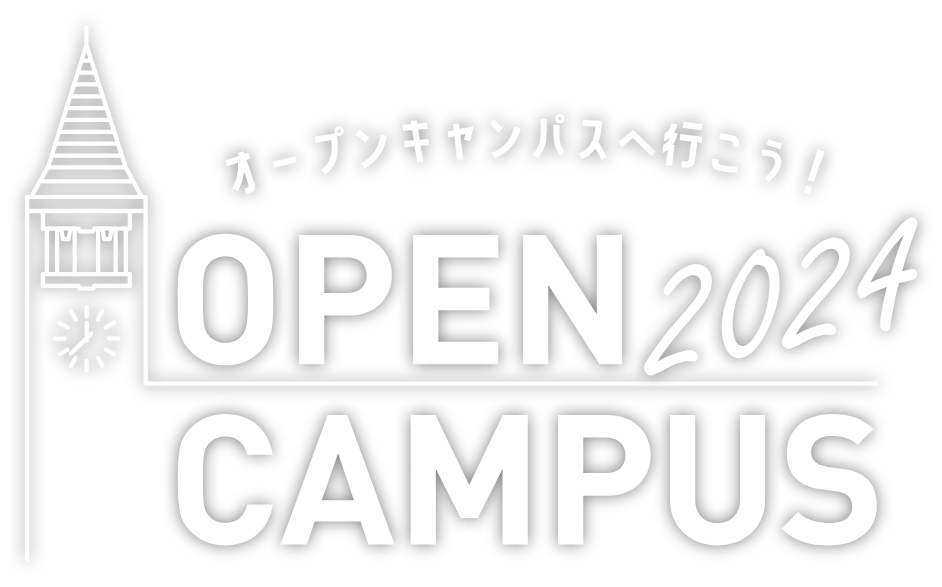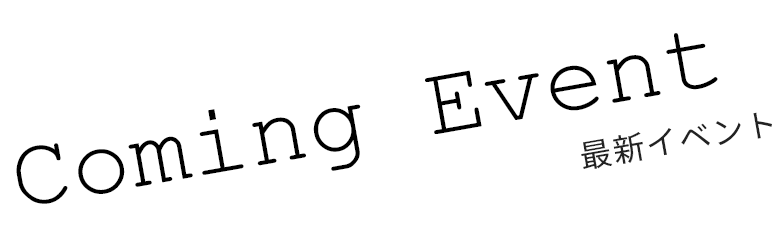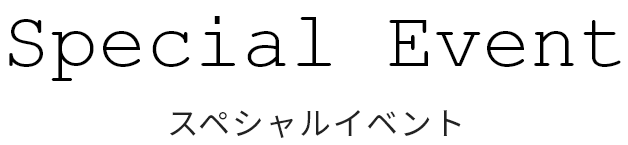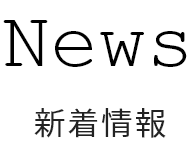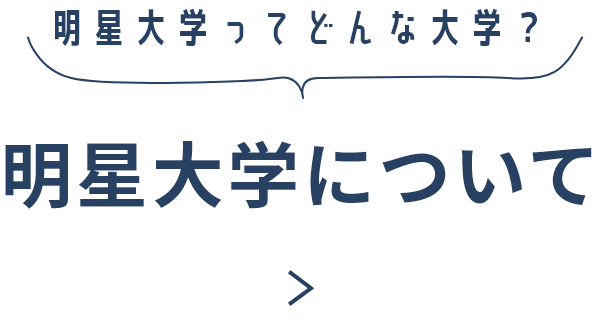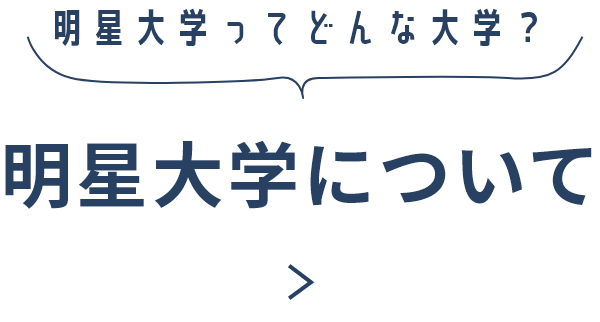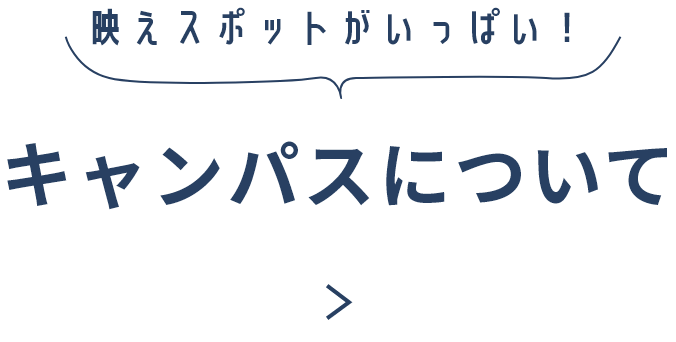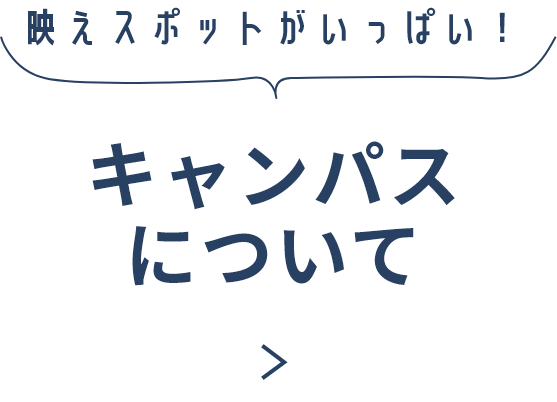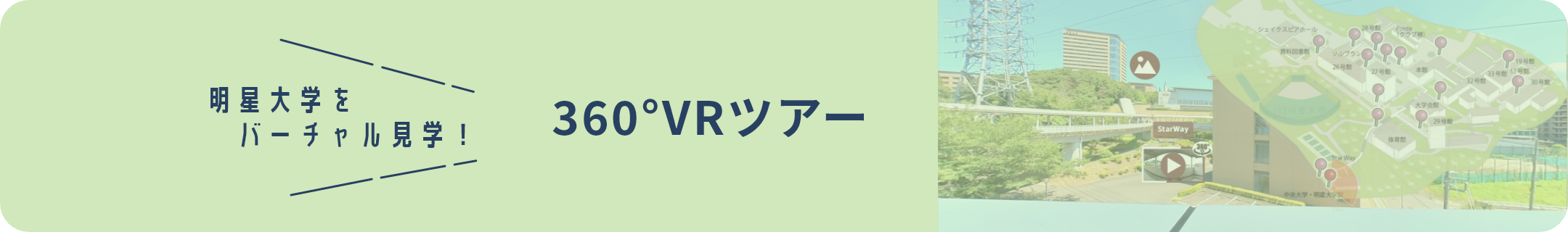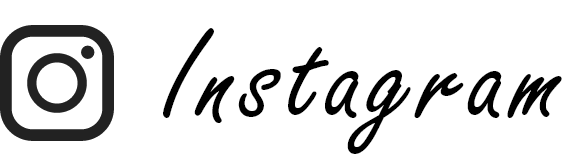- 2024.04.02 5月26日(日)オープンキャンパスの申し込みを開始しました!
- 2024.02.29 オープンキャンパス2024の情報は3月中旬頃更新予定です!
- 2024.02.13 【受験生のみなさん】3/2(土)一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜受験者・合格者対象 大学見学会のお知らせ
- 2023.12.18 12/23(土)オープンキャンパス イベントスケジュールを公開しました!
- 2023.11.22 12/23(土)オープンキャンパスのチラシ完成!
- 2023.10.10 【高校1・2年生のみなさん】12/23(土)のオープンキャンパス参加受付を開始しました!
- 2023.08.15 8/16(水)オープンキャンパスは予定通り開催します!
- 2023.08.07 8月16日(水)、19日(土)オープンキャンパス当日スケジュールを公開しました!
- 2023.07.21 7月23日(日)オープンキャンパス当日スケジュールを公開しました!
- 2023.06.08 7月23日(日)オープンキャンパス参加受付を開始しました!
- 2023.05.25 5月28日(日)オープンキャンパス当日スケジュールをイベント詳細ページで公開しました!
- 2023.04.10 5月28日(日)オープンキャンパス情報更新しました!
- 2023.04.10 明星大学 オープンキャンパスサイト2023オープン!